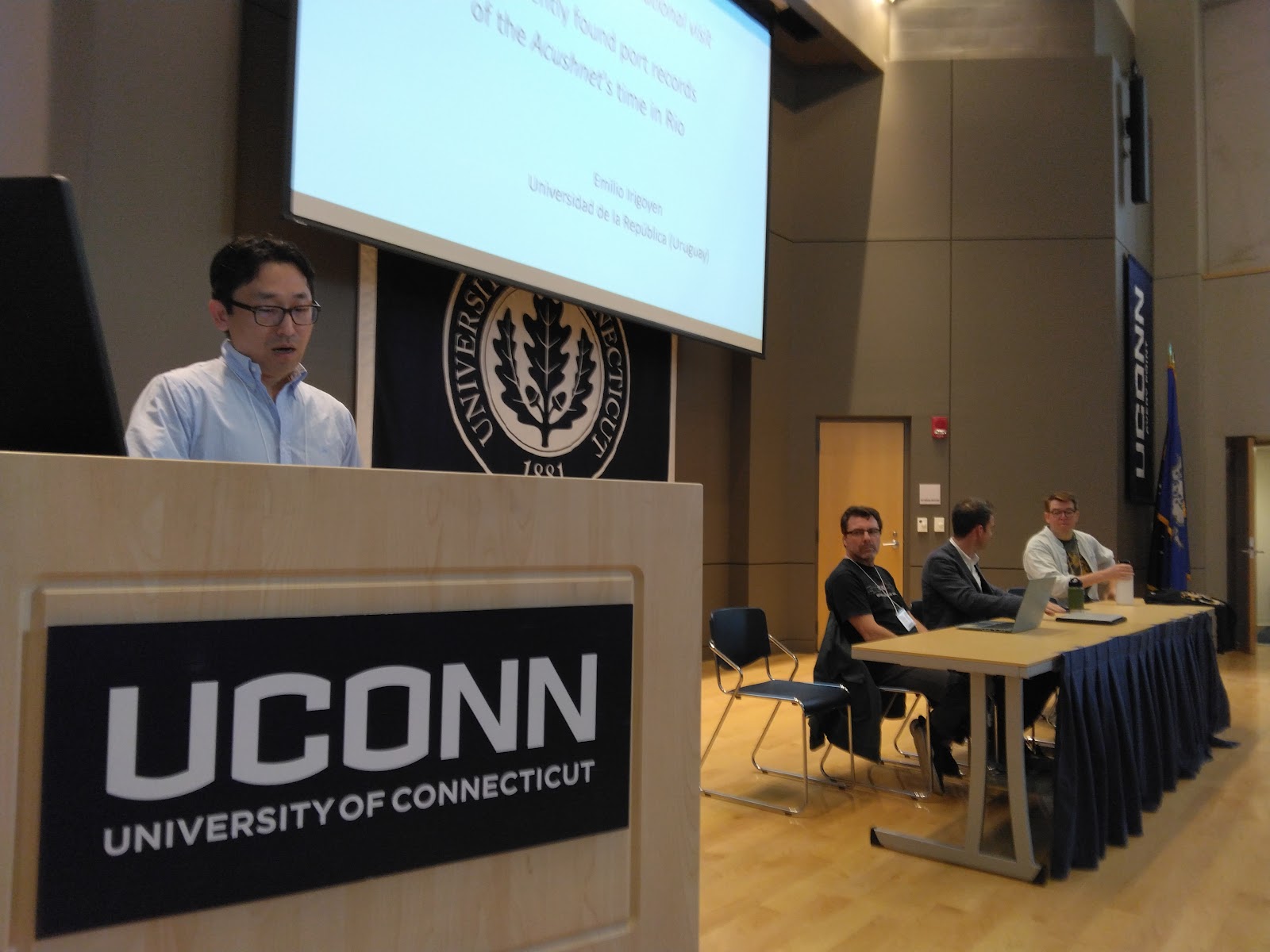【書いたもの】
*査読論文
Furui, Yoshiaki. "Ventriloquizing the South: Reading Melville across the Civil War." Journal of American Studies, vol. 58, no. 4, 2024, pp. 489-510.
*共著
「痛みをまなざす:ディキンソンの脱制度的想像力」『病と障害のアメリカンルネサンス: 疫病、ディサビリティ、レジリエンス』髙尾直知・伊藤詔子・辻祥子・野崎直之編著、小鳥遊書房、2025年、pp. 171-94。
*分担執筆
『アメリカ文学史への招待ーー豊饒なる想像力』橋本安央・ 藤井光・ 坂根隆広編著、法律文化社、2025年(「ヘンリー・デイヴィッド・ソロー」「ウォールデンーー『森の生活』を担当)。
*学会プロシーディングズ
「Breaking Englishーーメルヴィルのテクストスケープ」『Sky-Hawk: The Journal of the Melville Studies of Japan』第12巻、2025年、pp. 69-71。
【口頭発表】
*学会発表
1、「博論から単著へーーアメリカ大学出版局奮闘記」シンポジウム「論文投稿と学術書出版のジオポリティクスーー海外ジャーナルとアメリカ大学出版局」、 筑波大学、2025年3月14日。
2、"No Asylum for Whalers: Japan in Moby-Dick." Oceanic Melville: Fourteenth International Melville Society Conference, University of Connecticut, 2025年6月17日.
*その他
1、「メルヴィル・アメリカ・世界文学」 福嶋亮大氏との対談、立教大学アメリカ研究所公開研究会、2025年10月14日。
2、「The Blue Humanities:海、みずうみ、川の環境人文学」 宮地尚子氏、山本洋平氏とのラウンドテーブル、明治大学、2025年12月5日。
【受賞】
アメリカ学会第6回中原伸之賞(『誘惑する他者』に対して)
また、来年以降の予定、進行中の仕事は以下の通り。
【共著】
1、A Cultural History of Solitude in the Nineteenth Century, edited by Catherine Samiei and Julian Stern, Bloomsbury (2026年に出版予定。19世紀アメリカ文学における孤独を論じたチャプターを寄稿)
2、 The Routledge Companion to Herman Melville, edited by Cody Marrs and Brian Yothers, Routledge (2027年に出版予定。『白鯨』を中心に、メルヴィル作品における日本表象を論じたチャプターを寄稿)
3、日本の論集にメルヴィル『ピエール』論を寄稿。2026年に出版予定。
【口頭発表】
1、2026年3月にアメリカの学会でメルヴィル「バートルビー」に関して発表予定。
2、2026年6月に国内のシンポジウムでメルヴィル『戦争詩集』について発表予定。
3、2026年7月に国内のシンポジウムでディキンソンの詩について発表予定。
【査読中の論文】
1、ポーのGordon Pym論を海外ジャーナルに投稿、査読中。
2、ホーソーン論を海外ジャーナルに投稿、査読中。
3、ブロックデン・ブラウン論が海外ジャーナルでRevise & Resubmitとなり、改稿中。
ここ2年は校務と学会仕事が本当に忙しく、特に今年は重い役職に就いていたため、思うように研究する時間を取ることができませんでした。とはいえ、こうまとめてみると忙しいなりに研究は頑張ったように見えます。細切れの時間でも研究できるよう、時間の使い方を見直す時期に来ているのを感じます。
今の自分のプライオリティは、なにより海外の有力ジャーナルで英語論文を出すことです。それがうまくいけば、次のアメリカで出す単著に繋げることができるはずで、来年はなんとかアクセプトをもぎ取りたいです。忙しさを言い訳にせず、頑張ります。